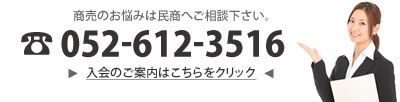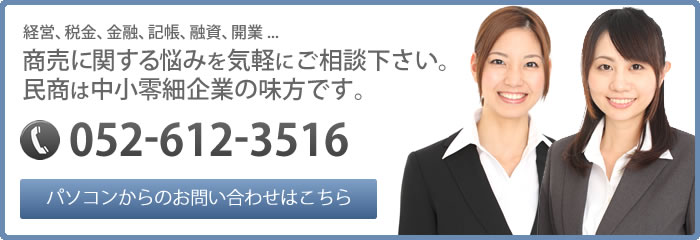こんな時は迷わず、民商へ
- 今年初めての申告で心配
- 消費税のしくみが良くわからない
- 決算で困っている
- 自分でやりたいが、相談するところがない
事前通知が原則に
国税通則法「改正」で事前通知が法定化されました。
事前通知すべき事項は、
- 調査を開始する日時
- 調査を行なう場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- 納税者の氏名・住所
- 税務職員の名前・所属部署
- 日時・場所は変更できること
- 他に疑いが出た事項は改めて通知しなくても調査できる
という説明の10項目です。
このうちどれか一つでも欠ければ適正手続きに反し、事前通知したことにはなりません。
事前通知なく税務署員が訪問してきた場合、「なぜ例外規定にあたるのか」「事前通知をしないこととした理由を開示させる」ことを求めることは当然です。
税務調査事前通知チェックシートをダウンロードして税務調査に備えましょう。
税務調査では、「とことん味方」
一般の税務調査は、任意調査と言われ、税務当局も「納税者の理解と協力を得て行う」事を前提にしています。
しかし、実際には、納税者の主張を無視した、横暴な調査が横行しています。
税務調査の横暴から納税者の権利を守るために、本人と一緒になってとことんたたかい、納得の行く調査をすすめます。
自分でする記帳・決算は経営の羅針盤です
申告納税制度は、国民を主人公とする憲法の精神を税法にいかしたものです。国税通則法16条は、「納税者がする申告により税額が確定することを原則とする・・」として納税者に税額の確定権をゆだねているのはそのためです。
納税者が自ら「記帳し計算し申告する」という税法の原則を守り発展させる取り組みをすすめているのが民商です。
簿記教室やパソコン会計教室など様々な取り組みを通して「申告納税制度」の擁護発展に尽力しています。
税務調査について10の心得
国税通則法は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(16条)と憲法と同じように国民が主人公であることを規定しています。
税務調査においても、国民が主人公として丁重かつ親切に取り扱われなければなりません。税務調査は、法の定めに従って、納税者の承諾を得た上で、税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類などを調べるもので犯罪捜査ではありません。
国税庁も、税務運営方針で、「納税者の理解と協力を得ておこなう」こととしています。
1.自主申告は権利
 自主申告こそ納税者の基本的な権利です。
自主申告こそ納税者の基本的な権利です。2.相手の身分確認を
 税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること※所得税法236条、法人税法157条、消費税法62条5項
3.調査理由を確かめよう
 どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」
どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」※憲法13条・31条、第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4.不都合なら断りを
 突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すること」
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます。「事前に納税者に通知すること」※憲法13条・31条、第72国会で請願採択、国税庁の税務運営方針
5.承諾なしの侵入は違法
 納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「礼状なしで進入、捜索及び押収をうけることのない権利」
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「礼状なしで進入、捜索及び押収をうけることのない権利」※憲法35条 住居の不可侵
6.調査は目的の範囲に
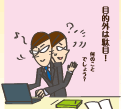 調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」※国税庁の税務運営方針
7.勝手な取調べは違法
 検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること。
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリことわること。※北村人権裁判・大阪高裁判決(1993年3月19日に確定)
8.信頼できる立会人を
 納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること。「立会い理由の青色取消は不当」
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること。「立会い理由の青色取消は不当」※春日裁判・東京高裁判決(1993年2月23日に確定)
9.承諾なしの反面調査は断る
 納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められた場合に限って行う」
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的に見てやむを得ないと認められた場合に限って行う」※国税庁の運営方針
10.印鑑は命
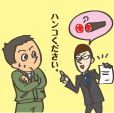 印鑑は命。税務署員に”捺印”をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐおさず、よく考えてからにすること。
印鑑は命。税務署員に”捺印”をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐおさず、よく考えてからにすること。※公務員の職権濫用罪 刑法193条
※「税務調査10の心得」をしっかり学習しましょう。
※「納税者の権利」「日常的な自主計算活動を」のパンフも販売しています。